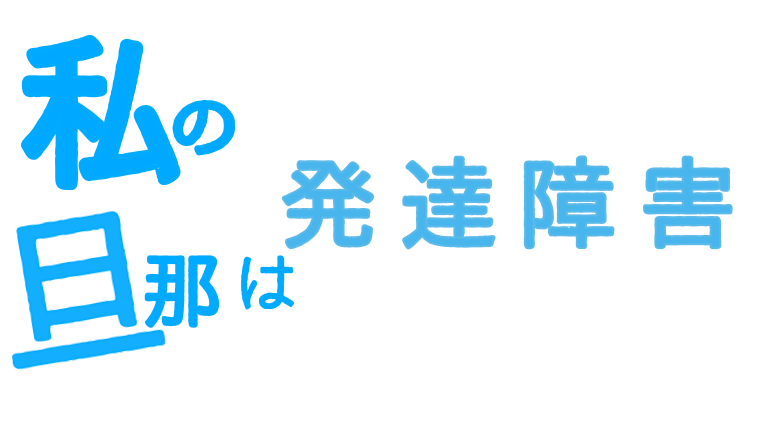※令和5年3月12日編集
※令和6年1月21日編集

発達障害(ASD+ADHD)と
診断されているネスケです
妻ネスケ子には「瞬間湯沸かし器」みたいと言われています。

妻のネスケ子です
私たちの紹介はコチラ
いきなりキレるネスケに日々困っています。
ネスケは、いきなり怒ります。
状況や背景を考えても怒る原因が分からない時もあれば、「なんでこんなことで怒るの?」と思うことで怒る時もあります。
『どんな時に怒るの?』と、怒る状況のパターンを書いた記事もあるので、お時間がある時に読んで頂ければと思います。
今回の記事は
発達障害の特性を持っている方の『キレる』とか『攻撃性』の部分を、わたしが調べたことやネスケの場合として書いていこうと思います。
発達障害の特性を持つ方全てに当てはまるということではなく、あくまでもネスケの場合なので参考程度に読んでいただければと思います。
しかし発達障害の特性を持つ方の中には、ネスケ同様に怒りっぽい方が多いようです。

もう本当に沸点低すぎる。
発達障害の特性が原因の場合の「怒り」の原因

『怒りっぽい』や『怒り方』は、性格や育ってきた環境(家庭環境)などによっても違うものです。
発達障害の特性が関係している『怒り』の場合は、「そういう性格なんだ」というものとは違います。
あくまでも『特性から『怒り』になってしまう』ものです。
今回は「すぐ怒る」ことについて書いていますが、怒りやすい(怒りっぽい)人だからといって発達障害というわけではありません。(逆を言えば、発達障害の特性を持っている方全てが怒りやすいというわけでもありません。何も言えない方(フリーズしてしまう方)もいます。)
ネスケとの日常生活の中で『怒っている(怒っているというか瞬間湯沸かし器)姿』は、ネスケの安定の姿です。
そんなネスケが、とくに『瞬間湯沸かし器のような怒り』が出てくる状態があります。
- 疲れやストレスが溜まっている時
- 睡眠不足の時
- 状況が分からず不安な時
こんな時は、びっくりするほどに瞬間湯沸かし器のように怒っています。
わたしでも、疲れやストレスが溜まり精神不安定な状態の時は怒りやすくなりますが頻度が違います。
頻度も違いますが程度も違って、抑えがきかずに『とてもしつこい』。
他にも『不安からの怒り』も多くあります。
発達障害の特性を持つ方は、知らず知らずのうちにストレスや疲れが溜まりやすいとも言われています。
本人が気づかない間にストレスが溜まり、些細なことでも『怒り』が出やすい状態になっていることが多いんです。

疲れやストレスがきっかけとなり、特性からの怒りが出てきます。
「衝動性」からの怒り
ADHD(注意欠如・多動症)の特性の1つ「衝動性」。
衝動的な怒りです。
ネスケも衝動的に怒ることが多く、落ち着いたときに「なんで怒ったんだろう?」と本人もわからない時があります。

「こんなことで普通怒る?」という些細なことでも怒るんだよね。
どこに地雷があるか、本当に分からない。
衝動性からの怒りは、家族などに対して無防備で過ごせる場面では『過度の怒り』になることが多くある。
普段は温厚なネスケも、家にいる時やわたしと2人で過ごしている時は怒りやすい。
まあ、家で過ごしている時やわたしといる時は無防備に過ごせているという見方もできますが、こちらとしては「もう本当に勘弁してくれよ。」と思います。
衝動性は「混沌性」ともとることができます。
ネスケが時々「頭の中が忙しい」と言う時があるんですが、頭の中が混沌としていて思考をまとめられないことも『怒り』に関係しているのかもしれません。
ASD(自閉スペクトラム症)にも『衝動性からの怒りはある。』と、わたしが読んでいる本にはありました。
『参考文書:(大人の発達障害 生きづらさへの理解と対処 (監修者:市橋秀夫))』
ASD、ADHDのどちらでも、感情の表し方がコントロールできない。
『怒り、悲しみ(落ち込み)以外の感情を表すのが下手』
そして、衝動性が強い方の怒りは一回怒り出すと止められなくなる。
『感情のメモリが小さい』ことからの怒り
ADHD(注意欠如・多動症)の特性を持つ方は、ワーキングメモリが少ないと言われています。
ワーキングメモリが小さいことを補うために、小さいワーキングメモリが複数あり小さい保存を分散させている。
分散はさせるけれど同時に保存を見る事が出来ない為に、保存したものが全て中途半端になる感じと、【睡眠専門医渥美正彦医師】のYouTube動画にありました。
そしてワーキングメモリが小さいのと同じく『感情のメモリ』も小さいと説明されていました。
この感情のメモリの中の、『ネガティブ問題』も小さいために『すぐにいっぱいになって、ボンッ!と爆発する』というイメージらしいです。
ワーキングメモリの説明の中で、わたし的にはこの動画内での説明が一番しっくりきました。
爆発前の感情を処理することが苦手だから、すぐに爆発してしまう。
わたしとネスケの場合を上の説明を使って考えてみましょう。
わたしのネガティブ問題のメモリはネスケに比べて大きいので、ネガティブな感情が溜まっていく間に、前に保存された感情を上手く処理できる。
爆発までには至らない、もしくはすぐには爆発しないということだと思います。
あ、ネスケに対しての不満が溜まる速度は速いので、処理しきれない時が多いですが(笑)
ADHDの特性を持つ場合の脳機能
発達障害は『脳の機能障害(アンバランス)』と考えられています。
ADHD(注意欠如・多動症)は「前頭前野と側坐核という部位で、ドーパミンがうまく働いていないのでは?」と言われているようです。
ちなみに、神経伝達物質は神経細胞に回収されて再利用される。
けれど、『ADHDでは数多くの神経伝達物質のうち、特にドーパミンと呼ばれる神経伝達物質が脳内で不足している。不足している状態で、ドーパミンの再取り込みが行われると、神経伝達に利用できるドーパミンが枯渇して脳が正常に機能しなくなってしまう。』という事が今現在分かっていることです。
前頭前野は『プラン、実行、想像、思考、感情のコントロール』などの機能を担う、脳の司令塔のような部位です。
なので、『スケジュール通りに進められなかったり、管理が出来ずに失くし物、探し物が多い、やりたい事を始めてしまったり、やろうと思っても行動できなかったり』といったことに繋がるようです。
側坐核は、『抑制などの機能を担う、目の前の楽しみに飛びつかないようになど、衝動性をコントロールする部位です。
『だめだと思っても(分かっていても)止められない。』ということになるようです。
感情のコントロールができない
すぐ怒ったり気分が態度に表れやすいのが、ADHD(注意欠如・多動症)の特性を持っている方。
気分が態度に直結しやすい特性となって現れることもある。と、『発達障害の人が見ている世界(著者:岩瀬利郎)』に書かれていました。
ADHDの人の衝動性は、気分が態度に直結しやすい特性となって現れることもあり、これは情動をコントロールするなど、理性を司っている大脳皮質の働きの弱さが一因と考えられています。
引用元:発達障害の人が見ている世界(著者:岩瀬利郎)(出版元:アスコム)
ネスケも本当に些細なことでも怒ることが多く、正直「なんて心の狭い人なんだ」と思ったことも少なくはありません。
睡眠不足やストレスが溜まっている時は、とくに感情のコントロールができない状態となります。
『認知のゆがみ』からの怒り
発達障害の特性を持つ方は、人より認知にゆがみが生じやすい。
私見ですが、ASD(自閉スペクトラム症)の特性を持つ方がとくに多いように感じます。
認知のゆがみは、『10つの思考パターン』があります。
認知のゆがみがあるため、相手の言動を間違った意味で捉えてしまうことがあります。
とくに『ネガティブな意味』として捉えることが多いので、ネスケの場合は『怒り』に繋がることが多いです。
認知のゆがみについて書いた記事があるので、お時間がある時などに覗いてみてください。
ネスケの通院する病院の心理士さんと話している時に「~は、ネスケさんの認知のゆがみからくるものです。」と、『認知のゆがみ』という言葉は何回か聞いていました。
ネスケの怒る場面を思い出してみると、認知のゆがみから来る『怒り』が多いことに改めてびっくりです。
現在では、少しずつ認知のゆがみが改善されているネスケ。
- 自分の考えを書き出すようになった
(問題が起こった時も書き出すようになった) - わたしの書いたアメブロを読んで気づく
- 冷静になったときに、お互いの感じたことを話すようになった
自分の考えとわたしの考えを『文章で見比べる』ことなどで、自分の認知のゆがみに気づくことが増えたことにより改善されてきたのだと思います。
認知のゆがみは、発達障害の方だけに起こるものではありません。
今思いましたけど「俺ばっかり」というところと「周りが悪い」みたいに言うところは、認知のゆがみから来るものですね。
ASDの特性を持つ場合の脳機能
偏桃体、眼窩前頭野、側頭葉の働きが弱いことが分かっているようです。
(これらは、『社会脳』と呼ばれる事もあるそうです。)
扁桃体は、感情のコントロール
眼窩前頭野は、状況を読む、人の気持ちを推測するなど
側頭葉は、言語の理解など
ASD(自閉スペクトラム症)の特性には『情報の入力と処理が上手くいかない』というものがあり、この部分の脳の機能に困難があると言われています。
情報というのは、『目から入った物を、脳に入力して、入力したものを処理して、それが何であるかという何らかの意味を付与する』
入力したものに意味を付与する部分に困難があると言われているのが、自閉症スペクトラムということです。
入力する時に困難があるというものではなく、処理する(それが何であるかという部分)時の障害がある。
入力に障害があると出力にも影響する。
【参考書籍】
『怒る』原因のまとめ

発達障害の特性を調べているときに、「怒り」について目にすることが多いのは
- 怒りっぽい
- 些細なことでもひどく怒る
- とにかく瞬間湯沸かし器
- 怒っている理由がわからない
などがあります。
ネスケを見ていると確かに怒りっぽい、とにかく瞬間湯沸かし器です。
発達障害の特性のことをあまり知らなかった頃は、「なんでこんなことで怒るのか理解できない。」と思う日が多かった。(今でも思うときは多いです。)
認知のゆがみからの『間違った捉え方』をして怒ることが一番多いかな?と思います。
ネスケの頭の中で『1人マジカルバナナ』をしている時もあります。

ネスケが瞬間湯沸かし器になっている時は、わたしの言葉はネスケの耳には届かないので落ち着いた頃に話を聞くことがあります。
ほとんどは、わたしの発言を間違って捉えて怒っています。
相手が怒っている時って、本人も一緒にいる人も不快ですよね。
ネスケの怒りやすい原因が特性だと分かっていても、わたしはとても辛い時があります。
原因が分かっていてもです。
- 怒っているネスケと接することからのストレス
- 理不尽な怒りに対してのストレス
- 理由を聞いても理解できない「怒り」へのストレス
- 悲しい気持ちになる
怒りに対してのあらゆる感情が沸いてきます。(ほとんどはネガティブな感情)
そんな時はネスケの特性に対してではなく、ネスケ自身が原因と思ってしまいます。
『分かっていても』怒られたという辛い気持ちだったり、不快な気持ちは消えないものです。
認知のゆがみからの怒りが多いなら、認知の改善を考えることも大切だと感じています。
配慮を一方的に求めるのではなく、配慮を求める側もやはり改善することが大切。
ネスケは診断されて4年経った頃から、わたしに配慮を求めるだけではなく『自分自身も努力が必要だ。』と言うようになりました。
- アンガーマネジメントの必要性
- 認知のゆがみの改善の努力
- 問題が起きたときの振り返り
- わたしの意見とネスケ自身の意見の照らし合わせ
これらをネスケ自身が考えるようになりました。
ただし『メルトダウン』を起こした時だけは、どうにもならないのでフェードアウト一択です。
メルトダウンからの怒りは、身近にいると危険なのでその場から離れるようにしています。
感情が爆発しているメルトダウンは、ネスケ曰く「止められない」と言い「その時に殴られたら殴り返してしまうかもしれない。殴らないとも言えない。」とも言います。
ネスケの怒りに対してわたしが気をつけていることは
『怒り』の原因(原因となる特性)を知らなかった時よりは、もやもやが減ってきている気がします。
気をつけることや、相手へのアドバイスや意見も変わってきました。
一方的に身近な方が配慮をするのではなく、特性を持つ方も配慮をすることが必要だと思います。